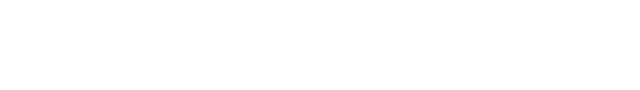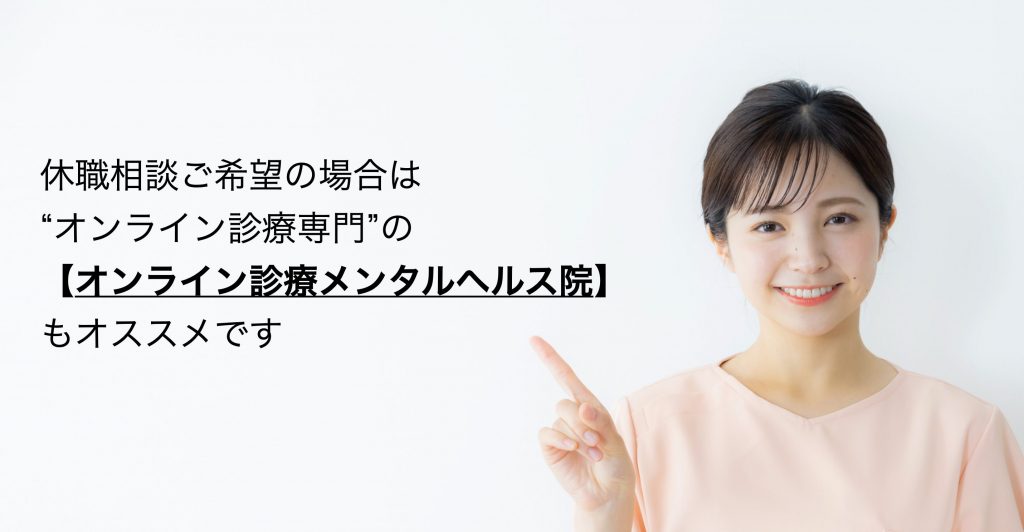分離不安症候群とは??
分離不安症候群(Separation Anxiety Disorder, SAD)は、愛着のある対象から離れることに対して過度な不安や恐怖を感じる精神的な障害です。
この障害は、幼少期や思春期の子どもに多く見られますが、成人にも発症する可能性があります。
愛着対象は主に親や保護者、配偶者、恋人などが含まれます。
以下では、この障害についてさらに詳しく解説します。
分離不安症候群の特徴
分離不安症候群は、愛着対象からの分離に伴う不安感が通常の発達段階を超えて強く、日常生活に支障をきたす点が特徴です。特に、以下のような点が注目されます。
-
年齢に不適切な症状
通常、幼児期や幼少期には親や保護者に対する依存や分離不安が見られます。しかし、分離不安症候群では、通常の発達段階を超えた年齢でも同様の症状が持続します。 -
持続性
症状が一時的ではなく、持続的に続くことが特徴です。DSM-5の診断基準では、子どもにおいては少なくとも4週間、成人においては少なくとも6か月以上の症状の持続が診断の要件となります。 -
成人型分離不安症候群
以前は子どもに限定された障害と考えられていましたが、現在では成人にも発症し得ることが知られています。成人型では、主にパートナーや恋人、子どもへの過剰な不安が見られます。
分離不安症候群の原因
分離不安症候群の原因は単一ではなく、遺伝的要因、環境的要因、心理的要因が複雑に絡み合っています。
1. 遺伝的要因
分離不安症候群は、遺伝的な要因が関与している可能性があります。家族歴に不安障害やうつ病がある場合、分離不安症候群の発症リスクが高まるとされています。
2. 環境的要因
環境要因は、分離不安症候群の発症において重要な役割を果たします。以下が主な要因です:
- トラウマ的経験
家族の死別、親の離婚、自然災害、病気などのストレスフルな出来事が引き金となることがあります。 - 過保護な養育
過度に保護的な養育スタイルは、子どもの自立心を妨げ、不安を助長することがあります。 - 分離経験
入院、親の長期不在など、幼少期における頻繁な分離経験が影響を与える可能性があります。
3. 心理的要因
- 気質
高い感受性や内向的な性格の持ち主は、分離不安症候群を発症しやすい傾向があります。 - 脳の神経伝達物質の異常
セロトニンやノルアドレナリンの働きの異常が、不安感の増大に寄与するとされています。
分離不安症候群の症状
分離不安症候群には、心理的、身体的、行動的な症状が含まれます。これらの症状が組み合わさり、生活の質を大きく損なうことがあります。
1. 心理的症状
- 過度な心配
愛着対象に災害や事故などの悪いことが起こるという不安が強く、離れることを避けようとします。 - 見捨てられる恐怖
愛着対象が自分を捨てて戻らないのではないかという恐れ。 - 分離への抵抗
対象から離れることを強く嫌がり、感情的に不安定になることがあります。
2. 身体的症状
- 身体的不調
不安が高まると、頭痛、腹痛、吐き気、動悸などの身体症状が現れます。 - パニック発作
分離に対する恐怖が極端な場合、息苦しさやめまいを伴うパニック発作が発生することもあります。
3. 行動的特徴
- 一人になることの拒否
夜に一人で眠ることや、親や保護者がいない場面での活動を極端に嫌がります。 - 執着行動
対象に対する頻繁な連絡や、物理的な距離を保つための執着行動が見られます。
診断基準
分離不安症候群の診断は、主にDSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)の基準に基づきます。以下のような症状が持続的に見られる場合、診断が下されます:
- 愛着対象から離れることに対する過剰な恐怖や不安
- 分離を避けるための強い抵抗や拒絶
- 不安に伴う身体症状の出現
- これらの症状が年齢に不適切で、社会的・学業的機能を損なう
- 子どもでは4週間以上、成人では6か月以上続く
治療方法
分離不安症候群の治療では、心理療法と薬物療法の組み合わせが有効です。
1. 心理療法
- 認知行動療法(CBT)
不安を引き起こす思考パターンを修正し、愛着対象からの分離に対する適応を促す方法です。段階的に分離に慣れるエクスポージャー療法も含まれます。 - 遊戯療法(子ども向け)
子どもが遊びを通して感情を表現し、不安を和らげる方法。 - 家族療法
家族全体が問題解決に取り組むことで、子どもの不安を軽減します。
2. 薬物療法
- 必要に応じて、抗不安薬や抗うつ薬(例: セロトニン再取り込み阻害薬〈SSRI〉)を使用します。これらは不安の根本的な原因に働きかける役割を果たします。
予防と生活の工夫
1. 子どもへの対応
- 子どもが安心して分離体験を行えるよう、徐々に自立を促します。
- 親自身が冷静に対応し、不安を軽減するモデルとなることが重要です。
2. 成人への対応
- 分離不安の対象となる関係を見直し、適切な距離感を模索します。
- 社会的サポートを活用し、不安を軽減します。
3. リラクゼーション
深呼吸、ヨガ、瞑想などのリラクゼーション技法を日常生活に取り入れることで、ストレスを軽減します。
分離不安症候群は、適切な支援と治療を受けることで、症状を改善し、安定した生活を取り戻すことが可能です。
早期に専門家に相談し、支援を受けることが大切です。
■オンライン診療メンタルヘルス院について■
休職相談を扱う"オンライン診療専門"の
「オンライン診療メンタルヘルス院」もあります。
休職について悩まれている方は、お気軽にご相談ください。