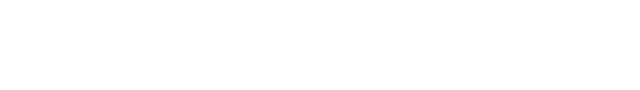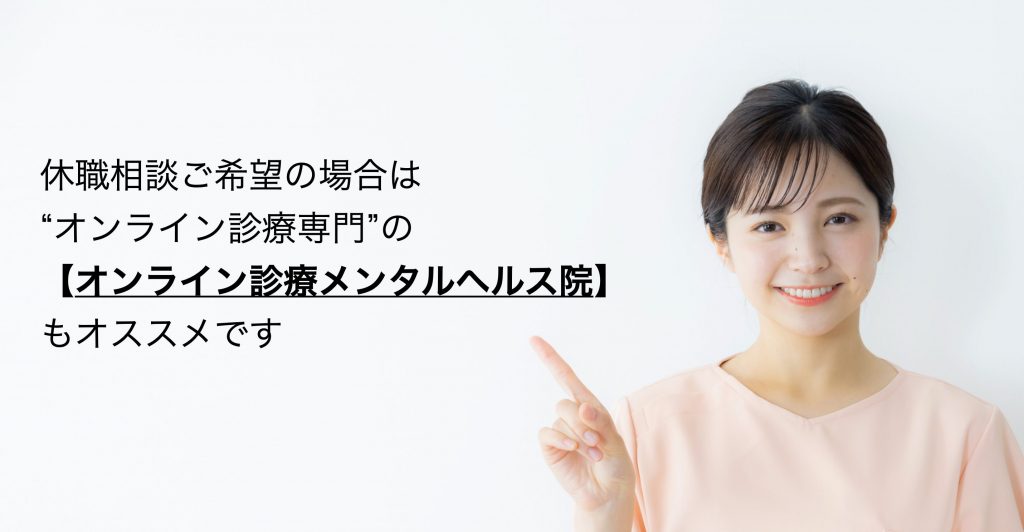退職後でも傷病手当金はもらえる?条件と手続き完全解説
1. はじめに
退職という人生の節目は、新しい生活への期待とともに、経済面や健康面での不安も伴います。特に、退職の前後で体調を崩した場合、「収入が途絶えてしまったらどうしよう」と心配になる方も少なくありません。
そのようなときに頼りになる制度のひとつが「傷病手当金」です。これは、病気やけがによって働けない期間に生活を支えるために設けられた仕組みで、現役時代に加入していた健康保険から給付されます。
しかし、実際には「退職後でも受け取れるのか?」という点で多くの人が誤解を抱いています。退職したあとでも継続して支給される場合がある一方、条件を満たしていなければ一切受け取れないこともあります。
本記事では、傷病手当金の基本から、退職後に受給できるパターン・できないパターン、申請の流れや注意点までを整理して解説します。あわせて具体的な事例を交えながら、自分の状況に当てはまるかどうかを判断できるようにご案内していきます。
2. 傷病手当金の役割と仕組み
退職後に受給できるかどうかを考える前に、まずは「傷病手当金とはどのような制度なのか」を押さえておきましょう。制度の目的や仕組みを理解しておくと、その後の条件や手続きも分かりやすくなります。
2-1. 制度の目的
傷病手当金は、病気やけがで働けなくなり、給与が支払われないときに生活を支えるための制度です。労災保険が「業務上の災害」を対象とするのに対し、傷病手当金は私生活での病気やけがによって労務不能となった場合をカバーします。
つまり、「病気で働けない間の所得補償」が目的です。
2-2. 支給要件
傷病手当金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
-
労務不能であること
医師により現在の仕事を続けられないと判断されていること。 -
待期期間を満たしていること
連続する3日間を含め、4日以上仕事を休んでいること。 -
給与の支払いがないこと
休業中に給与が一部でも支払われた場合、その分は差し引かれます。 -
健康保険の被保険者であること
国民健康保険では原則として対象外で、会社員や公務員が加入する健康保険組合・協会けんぽでの制度です。
2-3. 支給額と期間
-
支給額:標準報酬日額の3分の2相当額
-
支給期間:最長1年6か月(同じ傷病について通算)
休業開始から1年6か月のあいだに何度か復職・再発を繰り返した場合でも、同じ病気・けがであれば合計で1年6か月が上限となります。
2-4. 在職中の休職との違い
在職中に休職する場合でも傷病手当金を受けられますが、その際は「会社からの給与や休職手当」との調整が必要です。会社が一定の給与を支給している場合には、その額を差し引いた分だけが支給されます。退職後の場合は給与の支払いがなくなるため、調整が生じない分、制度の役割がより大きくなります。
2-5. 有給休暇との関係
有給休暇を取得している間は「給与が支払われている」とみなされるため、傷病手当金は支給されません。したがって、実際には「有給休暇を消化 → 有給がなくなった時点で傷病手当金を申請」という流れをとるケースが一般的です。退職前に有給休暇をまとめて取得した場合も同様に、その期間中は対象外となります。
このように、傷病手当金は「働けない間の生活を守る仕組み」であり、退職後に受給できるかどうかは、この基本条件がどの時点で満たされているかによって決まります。
次章では、退職後でも受給できる具体的なパターンについて見ていきましょう。
3. 退職後でも受給できるパターン
「退職してしまったら、もう傷病手当金はもらえないのでは?」と思う方も多いでしょう。確かに退職によって健康保険の資格はなくなりますが、一定の条件を満たせば退職後も受給を続けられるケースがあります。ここでは代表的なパターンを整理します。
3-1. 退職前から給付を受けていた場合
すでに在職中に傷病手当金を受給していた場合は、退職後も支給が継続されます。
例:退職の数か月前からうつ病で休職しており、在職中から傷病手当金を受給していた → 退職後も残りの期間は支給が続く。
3-2. 退職日にすでに労務不能であった場合
退職時点で「働けない状態」にあり、待期期間(3日間)が完成していれば、退職後に新たに傷病手当金を受け取ることができます。
例:退職日の直前から腰痛で勤務できず、医師により労務不能と診断されていた → 退職後も支給対象となる。
3-3. 健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合
退職後に給付を受けるためには、在職中に 継続して1年以上健康保険に加入していたこと が条件です。
例:勤続2年で退職し、退職日に労務不能であった → 条件を満たしているため、退職後も支給可能。
3-4. 注意すべきポイント
退職後に受給できるのはあくまで「退職日に労務不能であった場合」に限られます。
-
退職日まで通常勤務をしていた
-
退職後に初めて病気が見つかった
といったケースでは、傷病手当金は支給されません。
このように、退職後に受給できるかどうかの分かれ目は 「退職日当日に労務不能であったかどうか」 と 「健康保険加入期間が1年以上あるかどうか」 にあります。
次章では、この反対に「退職後に受給できないケース」について解説していきます。
4. 受給できないケース
退職後も条件を満たせば傷病手当金を受給できますが、反対に条件を外れてしまうと一切支給されません。ここでは代表的な「受給できないケース」を確認しておきましょう。
4-1. 退職後に病気やけがが発覚した場合
退職日に働ける状態であった人が、その後に病気やけがで労務不能になっても傷病手当金の対象にはなりません。
例:退職から2週間後に体調不良で診断を受けた場合 → 退職日当日に労務不能でなかったため、支給されない。
4-2. 任意継続被保険者になった場合
退職後に健康保険を継続する方法として「任意継続被保険者」がありますが、この制度には傷病手当金の給付は含まれていません。
つまり、任意継続に加入していても新たに傷病手当金を申請することはできません。
4-3. 国民健康保険に加入した場合
退職後に国民健康保険に切り替えた場合も、原則として傷病手当金はありません。
(一部自治体では独自の給付を設けている場合がありますが、ごく限定的です。)
4-4. 健康保険の加入期間が1年未満の場合
退職後に受給を続けるには、健康保険の被保険者期間が1年以上必要です。
勤続が短い場合は条件を満たせず、たとえ退職日に労務不能であっても給付を受けられません。
このように、退職後の傷病手当金は「退職日当日の状態」と「保険加入期間」が大きな分かれ目になります。特に「退職後に体調を崩した場合」「任意継続や国保に加入した場合」には、原則として受給はできない点に注意しましょう。
次章では、実際に申請する際の 具体的な手続きの流れ を整理します。
5. 申請の流れと必要書類
退職後に傷病手当金を受け取るためには、条件を満たすだけでは不十分です。申請の手続きをきちんと行わなければ給付は始まりません。ここでは、実際の申請の流れをステップごとに整理します。
5-1. 医師の証明を受ける
まずは主治医に診察を受け、「労務不能であること」を証明してもらいます。
傷病手当金には専用の申請書があり、その中に医師が記入する欄があります。診断書とは別扱いなので、必ず所定の様式で記載してもらう必要があります。
👉 医師には「傷病手当金の申請に使う書類です」と伝えるとスムーズです。
5-2. 元勤務先に証明を依頼する
在職中に給与が支払われていなかったことを証明するため、退職前の勤務先に申請書へ記入してもらう必要があります。退職後の申請であっても、退職日までの給与状況は会社でなければ確認できません。
退職後に会社に連絡するのは気が重いという人もいますが、必須の手続きです。
5-3. 健康保険組合または協会けんぽに提出
書類が整ったら、退職前に加入していた健康保険組合または協会けんぽに提出します。
ポイントは、退職後に国民健康保険へ切り替えていても、申請は退職前に所属していた健康保険へ行う という点です。
5-4. 支給決定と振込
審査の結果、条件を満たしていれば傷病手当金が支給されます。初回の支給は1~2か月ほどかかることもありますが、2回目以降は比較的スムーズになるのが一般的です。
5-5. 継続受給の場合の手続き
傷病手当金は1回の申請で終わりではありません。療養が長引く場合には、定期的に医師の証明を受けたうえで「継続申請」を繰り返す必要があります。
このように、退職後の傷病手当金の申請は 医師 → 会社 → 健康保険組合 の順で証明を得るのが基本の流れです。退職後は会社との関係が薄れるため、退職前にあらかじめ申請方法や窓口を確認しておくことが、スムーズに給付を受けるための重要な準備となります。
次章では、実際に受給するうえで気をつけたい注意点を解説していきます。
6. 注意すべきポイント
傷病手当金は退職後の生活を支える大切な制度ですが、制度を正しく理解していないと「受け取れると思っていたのに申請できなかった」という事態になりかねません。ここでは、申請や受給にあたって特に注意すべき点を整理します。
6-1. 支給期間は通算で1年6か月
傷病手当金は最長1年6か月まで支給されますが、これは「休んでいた期間」ではなく「支給開始日からの通算期間」です。
途中で職場復帰しても、同じ病気やけがで再度休んだ場合は、最初の支給開始日から1年6か月以内に限られます。
👉 「1年6か月間は必ずもらえる」と誤解しないよう注意が必要です。
6-2. 失業給付との関係
傷病手当金と雇用保険の失業給付は、同時には受け取れません。
ただし、失業給付には「受給期間延長制度」があり、病気やけがで働けない期間は申請により最大4年まで延長できます。そのため、まず傷病手当金を優先し、回復後に失業給付を受けるのが一般的です。
6-3. 生活設計と保険料の負担
退職後は健康保険や年金を自分で負担する必要があり、傷病手当金の給付額は給与の3分の2相当です。実際には手取り額が現役時代より減るため、家計の見直しや生活費の試算をしておくことが欠かせません。
6-4. 申請の遅れや不備に注意
医師や元勤務先の証明が必要なため、申請準備には時間がかかることがあります。書類の不備があると支給が遅れるケースも少なくありません。特に退職後は会社との連絡がとりづらくなるため、退職前に必要書類や連絡先を確認しておくと安心です。
6-5. ありがちな失敗例
実際によくある失敗例を挙げておきましょう。
-
失業給付を先に申請してしまった
→ この場合、傷病手当金と重複して受けられないため、本来もらえるはずの給付を逃してしまう。 -
退職日に労務不能の証明が取れなかった
→ 医師の診断が退職日以降の日付であれば、退職後の支給は認められない。 -
必要書類を準備せずに退職した
→ 元勤務先への連絡が取りにくくなり、手続きが大幅に遅れる。
これらはすべて「制度を正しく理解していなかった」「事前の準備が不足していた」ことで起きるトラブルです。
このように、退職後に傷病手当金を受給する際は「期間の数え方」「失業給付との関係」「生活費の見通し」「申請の正確さ」、そして「ありがちな落とし穴」に注意することが重要です。
次章では、実際のケースを取り上げて、受給できる場合とできない場合をより具体的にイメージしていきましょう。
7. ケーススタディ
制度の説明だけでは、自分が当てはまるのかイメージしにくいものです。ここでは、退職後の傷病手当金に関する代表的なケースを取り上げ、受給できる場合とできない場合を具体的に見ていきます。
ケース1:退職直前から休職していた人
Aさん(35歳・会社員)は、退職の2か月前からうつ病で休職しており、在職中から傷病手当金を受給していました。退職日も労務不能の状態が続いており、加入期間も3年以上。
結果:退職後も引き続き傷病手当金を受給可能。
この場合、最長1年6か月の範囲で残りの給付を受けられます。
ケース2:退職後に体調を崩した人
Bさん(40歳・会社員)は、退職までは通常勤務をしていましたが、退職後2週間で糖尿病が発覚。医師から労務不能と診断されました。
結果:受給不可。
退職日に労務不能ではなかったため、傷病手当金の対象になりません。国民健康保険に切り替えていても給付はありません。
ケース3:入社から半年で退職した人
Cさん(28歳・会社員)は、入社半年後に心身の不調で退職。退職日に労務不能と診断されました。
結果:受給不可。
退職日に労務不能であっても、健康保険の加入期間が1年未満であるため、継続受給の条件を満たしません。
ケース4:失業給付を先に申請した人
Dさん(45歳・会社員)は、退職日に腰痛で労務不能でしたが、まずはハローワークで失業給付を申請。その後、傷病手当金の存在を知りました。
結果:失敗。
失業給付と傷病手当金は同時に受けられないため、先に失業給付を申請したことで傷病手当金を受けられなくなってしまいました。
これらのケースから分かるのは、退職後に受給できるかどうかは「退職日当日の状態」と「保険加入期間」、そして「手続きの順序」が大きなカギになるということです。
次章では、本記事全体の要点をまとめ、安心して制度を活用するためのアドバイスをお伝えします。
8. 結論とアドバイス
退職後の傷病手当金は、条件を満たせば強い味方となる制度ですが、その一方で「退職日当日の状態」や「加入期間」といった細かい条件に左右されます。最後に、本記事の要点を整理しておきましょう。
8-1. 受給できるためのカギ
-
退職日に労務不能であること
-
健康保険に1年以上加入していること
-
在職中に待期期間を満たしている、または退職日以降も労務不能が続いていること
これらを満たせば、退職後も継続して傷病手当金を受け取ることが可能です。
8-2. 受給できない典型例
-
退職後に初めて病気が発覚した場合
-
任意継続や国民健康保険に切り替えた場合
-
健康保険の加入期間が1年未満の場合
-
失業給付を先に申請してしまった場合
このような状況では原則として支給されません。
8-3. 安心して制度を使うために
-
支給期間は「通算で1年6か月」であることを理解しておく
-
失業給付と併用できないため、順番を誤らないよう注意する
-
退職前に必要書類や会社への依頼方法を確認しておく
-
不明点は自己判断せず、健康保険組合や協会けんぽに相談する
退職という人生の転機に体調を崩してしまうと、経済的な不安は大きくなりがちです。しかし、制度を正しく理解し準備しておけば、傷病手当金は大きな支えとなります。
「自分は対象になるのか」と迷ったときには、まずは加入していた健康保険組合に確認してみましょう。安心して療養に専念するための第一歩は、情報を得て正しく活用することから始まります。
■オンライン診療メンタルヘルス院について■
休職相談を扱う"オンライン診療専門"の
「オンライン診療メンタルヘルス院」もあります。
休職について悩まれている方は、お気軽にご相談ください。