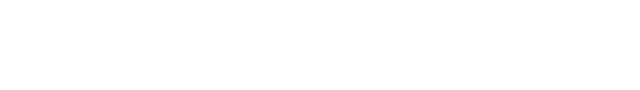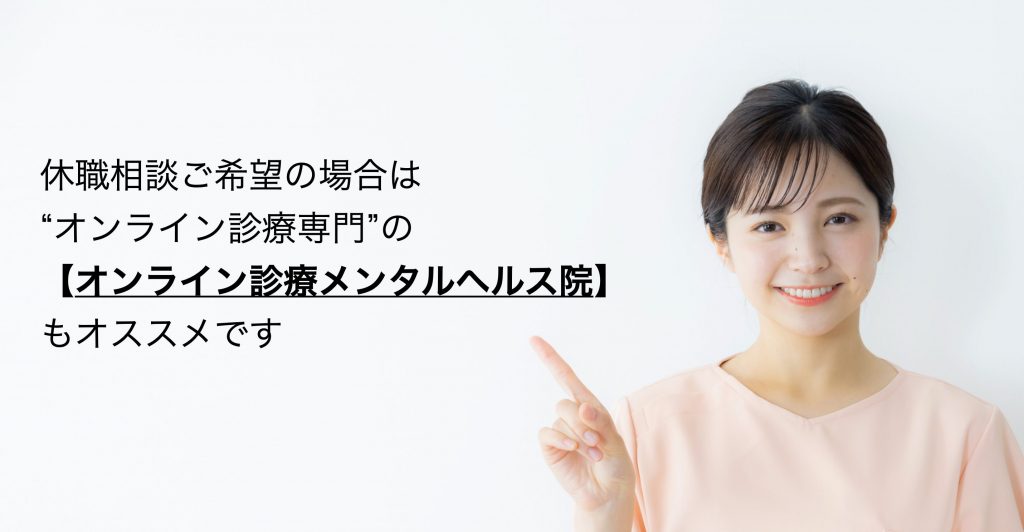「リベンジ退職」が心にもたらす影響とは?精神科医が解説
1. はじめに:なぜ今「リベンジ退職」が話題なのか
「リベンジ退職」という言葉を耳にしたことはありますか?
近年、SNSやネット記事でたびたび話題にのぼるこの言葉は、単なる退職とは異なるニュアンスを含んでいます。
たとえば、「ブラックな職場から逃れるように辞めてやった」「上司をぎゃふんと言わせて辞めた」といった、怒りや報復の感情を伴った退職のことを指す場合が多くなっています。
こうした「リベンジ退職」は、かつての日本社会ではあまり表に出ることがなかった感情や行動の表現であり、個人の尊厳を取り戻す手段として肯定的に語られることもあります。
一方で、衝動的な行動や、その後に残る精神的ダメージについては、まだあまり深く語られていません。
特に職場のハラスメントや過重労働、理不尽な評価などにより、心身に大きな負担を抱えたまま日々を過ごしている人にとって、「辞めることで自分を守る」という選択はとても重要です。
しかし、それが「復讐」や「仕返し」といった形で行動化されるとき、そこには癒されない傷や、処理されていない感情が潜んでいることも多いのです。
本記事では、リベンジ退職という現象を心理的・精神的な観点から読み解きながら、それが私たちの心にどのような影響を与えるのか、どのように向き合えばいいのかを、精神科医の視点から丁寧に考えていきます。
2. 「リベンジ退職」とは?
「リベンジ退職」とは、その名の通り“復讐”の気持ちを伴って行われる退職のことです。
単なる転職やキャリアチェンジではなく、職場での理不尽な扱いや上司・同僚からのパワハラ、過重労働への怒りなど、強い感情が動機となって「辞めてやる」「見返してやる」というかたちで行動に移されることが特徴です。
SNSを通じて可視化された「怒りの退職」
最近ではSNS上で「リベンジ退職してスッキリした!」「辞めた後、会社が回らなくなったらしい」といった投稿が拡散され、共感を集めています。
こうした投稿の背景には、多くの人が日常的に職場でストレスや不満を感じており、「本当は自分も辞めたい」「でも辞められない」という葛藤があることがうかがえます。
リベンジ退職の話題は、そうした人々の抑圧された感情を代弁する「代理的なカタルシス(感情の発散)」として、ある種の社会的役割を果たしているとも言えるでしょう。
リベンジ退職に至る心理状態
精神科的な観点から見ると、リベンジ退職の背景には、以下のような心理的状態が隠れていることがよくあります。
-
慢性的なストレス:長期間にわたる過剰な負荷や人間関係の摩擦
-
無力感と怒りの混在:「我慢しても何も変わらなかった」という諦めと、「こんな扱いはおかしい」という怒り
-
自己評価の揺らぎ:「自分には価値がないのでは」という不安と、それを跳ね返したいという衝動
こうした状態は、抑うつや不安障害の前段階であることも多く、「辞める」という選択が、心を守るための緊急避難的な行動として現れることもあります。
「辞めること=悪」ではない
大切なのは、「辞めること自体が悪いことではない」という視点です。
問題は、辞める動機が“怒り”や“仕返し”といった感情に大きく支配されているとき、その後も気持ちの整理がつかず、新たな環境でも心の不調を引きずることがある、という点にあります。
リベンジ退職を選んだ人の中には、「辞めたはずなのに、気持ちが晴れない」「あの上司の顔が今でも頭に浮かぶ」といった声も少なくありません。
本当に自分の心が望んでいるのは「復讐」なのか、それとも「安心できる場所で、自分らしく働くこと」なのか。まずはそこを見つめることが、より健やかな次の一歩につながります。
3. リベンジ退職の心理的メカニズム
「リベンジ退職をしてスッキリした」と語る人がいる一方で、「思っていたほど気持ちが晴れない」「時間が経つほど虚しさが残る」という声も聞かれます。
このギャップは、いったいなぜ生じるのでしょうか?
ここでは、精神科的な視点から、リベンジ退職に至る心の動きとその後の影響について見ていきます。
一時的な「カタルシス効果」とその限界
リベンジ退職には、強い怒りや悔しさを抱えた状態で、それを爆発的に外へ向けるという心理的特徴があります。
これによって、一時的に「スッキリした」「やっと自分を取り戻せた」というような解放感が得られることがあります。
この現象は「カタルシス効果」と呼ばれ、感情の抑圧が解放されたときに一時的に感じられる安堵のことです。
しかしこのカタルシス効果には限界があります。
抑圧されていた感情を表に出したとしても、根本的な傷(自己否定感、孤立感、不信感など)が癒されていなければ、再び同じ苦しさが心の中に戻ってくることが少なくありません。
自尊心の回復と、その裏にある傷つき
リベンジ退職には「自分の尊厳を守りたい」「軽視された自分を認めさせたい」という強い欲求が込められています。
これは、自尊心の回復を目指す自然な心の働きと言えるでしょう。
ただし、そのプロセスが他者に対する怒りや攻撃をベースにしている場合、最終的に得られるのは「勝利感」ではなく、「空虚感」や「自己嫌悪」であることも多いのです。
「強く見せようとしたけど、本当は傷ついていた」――そうした感情が、時間差で浮かび上がってくるケースもあります。
「やり返す」ことで癒えるとは限らない
復讐的な行動には、一時的な優位性や安心感があるように感じられます。
しかし、それは「本当に自分が望んでいたこと」とは限りません。
人の心は複雑で、怒りの裏には悲しみや孤独、不安が隠れていることがよくあります。
怒りを行動に変えることで、そうした感情を感じずに済ませてしまう――これは、一見すると心の防衛のようにも見えますが、実際には「本当の気持ち」と向き合う機会を失うことでもあります。
感情の整理を後回しにしないことの大切さ
精神科の現場では、「辞めたあとに気が抜けたようになった」「怒りが消えたら、涙が止まらなくなった」と訴える方に出会うことがあります。
これは、リベンジ退職によって一時的に抑えていた本音が、時間を置いて浮かび上がってくる自然なプロセスです。
だからこそ、退職という大きな転機の前後では、「行動」だけでなく「感情」の整理も大切になります。
自分の中にどんな傷や思いがあるのかを見つめ直すことが、次の職場や人間関係で、より自分らしく過ごすための土台になります。
4. リベンジ退職後に起こりうること
リベンジ退職は、その瞬間には強い解放感をもたらすことがあります。
「やっと抜け出せた」「言いたいことを言って辞められた」という実感は、長く我慢を強いられていた人にとって、大きな意味を持つでしょう。
しかし、精神科の視点から見ると、退職後の数週間から数ヶ月にかけて、心の揺れや落ち込みが起こることも少なくありません。
ここでは、リベンジ退職後に見られる主な心理的・社会的な変化についてご紹介します。
1. 思わぬ「虚しさ」や「後悔」が訪れることも
辞めた直後は爽快感があるものの、数日、数週間経つと「本当にこれでよかったのか?」という不安や後悔がふいに押し寄せてくることがあります。
-
「結局、自分だけが損をした気がする」
-
「誰にも理解されなかった」
-
「次の職場でも同じようなことが起きるのでは?」
これらの思いは、リベンジという行動の裏にあった“本当の傷つき”が、徐々に意識にのぼってくるプロセスの一部です。
怒りが落ち着いたとき、ようやく自分の内側の悲しみや寂しさと向き合うことになるのです。
2. 孤立感や社会的なつながりの喪失
職場は、単に労働する場所であると同時に、日常的な人間関係の場でもあります。
たとえストレスの多い職場だったとしても、毎日顔を合わせる人々や、ルーティンのある生活があったことが、心の安定につながっていたケースも少なくありません。
退職後、それらのつながりが一気に断たれることで、「社会から切り離されたような感覚」や「自分の居場所がなくなった感覚」に襲われることがあります。
3. 自己評価の低下と不安の増大
リベンジ退職をした方の中には、次第に以下のような思考に陥る人もいます。
-
「あんな辞め方をして、自分は未熟だったのでは」
-
「職歴に傷がついてしまったかも」
-
「次の職場でも嫌われたらどうしよう」
こうした不安や自己否定の感情は、時に抑うつや不安障害の入り口となることもあり、注意が必要です。
特に、元の職場でのトラウマ的な体験(パワハラ、いじめ、過労など)があった場合、心のダメージは時間差で顕在化することがあります。
4. 身近な人との関係に影響が出ることも
退職という大きな決断は、家族やパートナー、友人など、身近な人々との関係にも少なからず影響します。
特にリベンジ的な辞め方の場合、「どうしてそんな辞め方を?」と誤解されたり、「もっと穏便に済ませられなかったの?」という反応が返ってきたりすることもあります。
そうした反応に対してさらに傷つき、「わかってくれる人がいない」「自分の選択は間違っていたのかも」と孤立感を深めるケースも見られます。
5. 体調不良が現れるケースも
心理的なストレスが続くと、体に影響が出ることもあります。たとえば、
-
不眠
-
食欲不振
-
動悸、息苦しさ
-
倦怠感、頭痛、肩こり
などが続く場合、心身両面の疲弊が進行している可能性があります。
こうした体のサインを軽視せず、早めに医療機関やカウンセリングを利用することが大切です。
「辞めて終わり」ではない、心のプロセスを大切に
退職は人生の中でも大きな転機です。
とくにリベンジ退職は、強い感情をともなうため、その後の心のケアが置き去りにされがちです。
本当に大切なのは、「辞めたあと、自分をどう支えていくか」という視点です。
怒りや悲しみを一人で抱え込まず、時には信頼できる人や専門家とともに、自分の心を丁寧に見つめていく――そのプロセスが、次の一歩をより健やかなものにしてくれます。
5. 心を守るためにできること
リベンジ退職は、追い詰められた末の行動であることも少なくありません。
その背景には、長期的なストレスや理不尽な扱いへの怒り、悲しみ、無力感が積み重なっています。
だからこそ、辞める・辞めないという選択に関わらず、まずは「自分の心を守る」ことを優先してほしいと思います。
以下に、実際に役立つ具体的な方法をご紹介します。
1. 感情を書き出す:言葉にすることで整理される
怒り、悲しみ、焦り、不安……こうした複雑な感情が渦巻いているとき、まずは頭の中の思考や感情をノートに書き出すことをおすすめします。
-
何が一番つらかったのか
-
どのような場面で限界を感じたのか
-
本当はどうしたかったのか
-
自分の中の正当な怒りや悲しみは何か
書き出すことで、自分の中にある「本当の気持ち」が少しずつ見えてきます。これは、心の整理にとって大切な第一歩です。
2. 信頼できる人に話す:一人で抱えない
もし可能であれば、家族や友人、カウンセラーなど「あなたの味方になってくれる人」に気持ちを打ち明けてみてください。
話すことによって、「自分の感じていたことは間違っていなかった」と再確認できることがあります。
反対に、「もっと我慢すべきだったのでは?」など否定的な反応をしてくる人には、無理に話す必要はありません。
心を守るためには、話す相手を選ぶことも重要なセルフケアの一部です。
3. 自分を責めない:過去の自分を労う視点
退職を決めた、あるいはすでに辞めたあとに、「もっと冷静に対応できたのでは」「自分が悪かったのかもしれない」と、自分を責めてしまう人もいます。
しかし、あのときの自分にはそれが精一杯だったという視点を持つことは、とても大切です。
限界までがんばっていた自分に、まずは「よくがんばったね」と声をかけてあげてください。
4. 次の行動を急がない:心を休ませる時間を取る
退職後すぐに「次の仕事を探さなきゃ」と焦る方も多いですが、まずは心と体を整える時間をしっかり確保することを優先してください。
疲弊した状態のまま次の職場に飛び込むと、同じような苦しみを繰り返してしまうことがあります。
-
一日中、何もせず休む日をつくる
-
好きなこと・癒されることに時間を使う
-
睡眠と食事のリズムを整える
こうしたシンプルな生活の積み重ねが、回復のベースになります。
5. 専門的な支援を受ける:心のプロとつながる
リベンジ退職を検討している段階や、退職後に感情が不安定な時期には、精神科医や臨床心理士などの専門家と話すことがとても有効です。
-
うつや不安が疑われる場合には、診断や治療の対象となります
-
状況の整理、自己理解、再出発の支援が受けられます
-
医療機関では必要に応じて診断書の発行や休職支援も可能です
「こんなことで受診してもいいのかな」とためらう方もいますが、苦しいと感じていること自体が、支援を求める十分な理由です。
6. 「未来志向の辞め方」を選ぶ視点
もしまだ退職前であれば、「リベンジではなく、未来の自分のために辞める」という視点をもつことも大切です。
自分を守るため、前向きな環境に移るため、今の場所から距離を取る。それは決して「逃げ」ではなく、成熟した自己決定です。
まとめ
心が限界を迎える前に、自分を守る行動をとることは、とても大切なことです。
リベンジ退職という形で表れる感情には、誰にも否定できない背景や痛みがあるでしょう。
ただ、その後の人生をより良いものにするためには、感情を理解し、癒し、未来につなげていくプロセスが必要です。
一人で抱え込まず、安心できる支援とつながることで、あなたの心はきっと回復していきます。
6. 精神科医からのメッセージ
リベンジ退職という言葉には、強い感情が込められています。
怒り、悲しみ、悔しさ、そして「自分を大切にしたい」という願い。
そのすべては、人間らしく自然な感情であり、誰かが決して否定してよいものではありません。
けれど私たちの心は、ただ「行動」によって感情を昇華できるほど、単純でもありません。
辞めることで一時的に解放されても、傷ついた心が完全に癒えるには、やはり「時間」と「ケア」が必要なのです。
怒りの奥には、悲しみが隠れていることが多い
診療室ではよく、「あの上司が許せない」「絶対に見返したい」と強く語る方がいらっしゃいます。
けれど、少しずつお話を聞いていくと、怒りの奥には、「本当は認めてほしかった」「理不尽な扱いがただ悲しかった」という言葉が出てくることがあります。
怒りとは、自分の尊厳を守るための防衛反応でもあります。
その奥にある痛みやつらさに、どうか自分で気づいてあげてください。
「強さ」は、やり返すことではなく、自分を理解すること
本当に強い人とは、「誰かに勝つ」ことではなく、自分の内面と静かに向き合える人ではないでしょうか。
たとえば、自分の弱さを認めること。過去を責めすぎずに許すこと。
そして、「これからどう生きていきたいか」を、少しずつ言葉にしていくこと。
それは決して派手な行動ではないけれど、確実に、人生を変えていく大切な力です。
一人で背負いすぎないでください
リベンジ退職に至るまでには、誰にも言えない葛藤や、自分でもうまく説明できない気持ちが積み重なっていることと思います。
そうした気持ちは、話してみることで初めて整理されていくものです。
「こんなことで相談してもいいのだろうか」とためらわずに、必要なときは専門家を頼ってください。
精神科や心療内科、カウンセリングは、苦しみを整理し、次の一歩を支えるための場所です。
未来は「今ここ」から変えられます
今は混乱や不安の中にいるかもしれません。
でも、心は回復する力をもっています。そしてその回復は、怒りを糧にするのではなく、自分を大切にする選択によって進んでいきます。
立ち止まることは、決して後退ではありません。
今の自分を丁寧に見つめること。それは、未来のあなたを支えるもっとも大切な時間になるはずです。
7. まとめ
―「リベンジ退職」を選ぶ前に、心の声を聞いてみる―
ここまで、「リベンジ退職」というテーマを通じて、職場での苦しみや怒り、そしてその後に心がどのように揺れるのかを見てきました。
理不尽な扱いやパワハラに耐え、自分を守るために退職を決断すること。
その選択に込められた勇気と切実さを、私たちは決して軽視することはできません。
けれど、「辞めることで相手に一矢報いたい」「自分を軽んじた人間にダメージを与えたい」といった感情だけが先立ってしまうと、
本当に守るべき「自分の心」が、置き去りになってしまうことがあります。
大切なのは「どう辞めるか」ではなく、「どう回復していくか」
退職は、ただの終わりではなく、回復と再出発のスタート地点でもあります。
だからこそ、自分の中の怒りや悲しみと丁寧に向き合い、無理のない形で「次」に進む準備をしていくことが大切です。
もし今、強い怒りや絶望の中にいるのなら、まずはその気持ちを否定せずに、「それだけつらかったんだね」と自分に声をかけてあげてください。
あなたの人生は、あなた自身のものです
他人を変えることは難しくても、自分の人生の方向は、自分の選び方で変えていくことができます。
その第一歩は、「自分の心を知り、理解し、労わること」。
焦らず、比べず、少しずつでかまいません。
心が回復していくプロセスそのものが、次の人生を豊かにしてくれます。
必要なときには、専門的な支援を
心の傷は、目に見えにくく、気づかれにくいものです。
だからこそ、安心して話せる場所、整理できる時間、そして支えてくれる人が必要です。
当院では、退職をめぐる葛藤や不安、職場でのトラウマ的な体験についてもご相談いただけます。
ひとりで抱え込まず、いつでもご相談ください。
あなたの心の回復を、私たちは静かに、そして確かに支えます。
【最後に】
リベンジではなく、自己理解と未来志向の選択を。
本当の意味で自分を大切にする道を、一緒に探していけたらと思います。
■オンライン診療メンタルヘルス院について■
休職相談を扱う"オンライン診療専門"の
「オンライン診療メンタルヘルス院」もあります。
休職について悩まれている方は、お気軽にご相談ください。