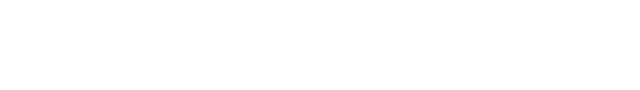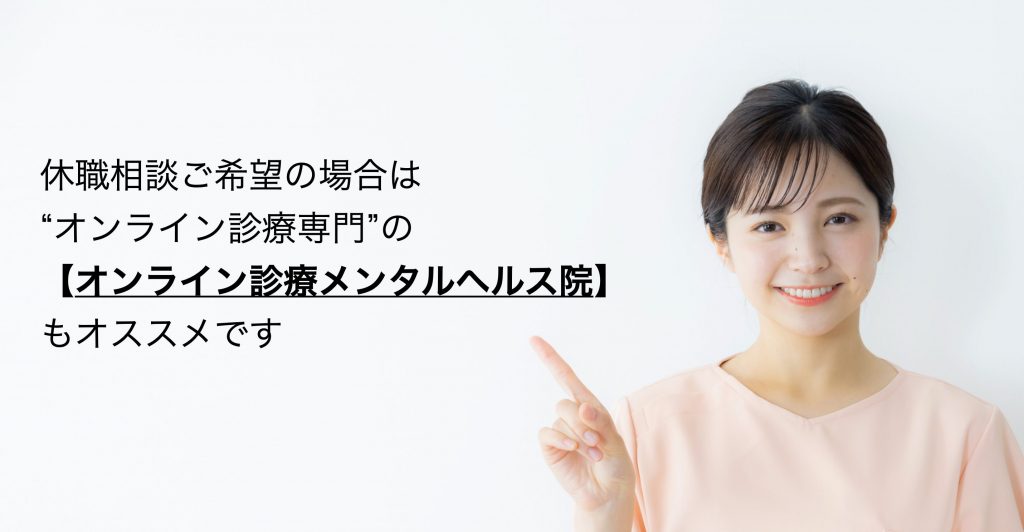「五月病かな?」と思ったら読む記事 ~こころが疲れやすい季節のセルフケア~
1. はじめに
春の風がやわらかく頬をなでる季節。桜が咲き、新しい出会いやスタートに胸をときめかせる人も多いことでしょう。
でもその一方で、「なんだか気分が晴れない」「最近ずっと疲れてる気がする」そんなふうに感じていませんか?
4月に環境が変わったばかりの人にとって、5月は心と身体がその変化についていけなくなる時期でもあります。
特にゴールデンウィーク明けには、ふと気が抜けたようにやる気が出なかったり、理由もなく憂うつな気分になったりすることがあります。
こうした状態は、一般に「五月病」と呼ばれています。
「病気」と言うと少し構えてしまうかもしれませんが、実はこれは医学的な診断名ではありません。
けれども、確かに心が疲れやすい時期であることは確かです。
そして、それに気づいてあげることは、自分を大切にする第一歩です。
この記事では、五月病の正体や、その背景にあるこころの動き、そして日々の中でできるセルフケアの方法をご紹介していきます。
「最近ちょっとつらいかも」「もしかして自分も五月病?」と感じている方が、少しでもほっとできるように。
そして、「自分だけじゃない」と安心できるように、やさしくわかりやすくお届けします。
2. 五月病とは?
「五月病」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。
でも実は、この言葉は医学的な診断名ではありません。
一般的には、4月に新しい環境へと踏み出した人が、5月頃になると感じやすくなる心や身体の不調をまとめて、そう呼んでいます。
たとえば、新社会人としてのスタート、進学や転職、引っ越し、部署異動など、春は何かと「新しいこと」が多い季節です。
最初のうちは緊張感とやる気でがんばれていても、少し時間が経つと、その反動で心身に疲れが出てくることがあります。
特にゴールデンウィークのような長めの休暇のあとに、「仕事に行きたくない」「朝がつらい」「集中できない」といった感覚が出やすくなるのです。
よく見られる症状の例
五月病の症状は人それぞれですが、たとえばこんなサインがあります:
-
朝、起きるのがつらくなる
-
やる気が出ない、何もしたくない
-
集中力が続かない
-
食欲が落ちたり、逆に過食気味になる
-
気分が沈んで、なんとなく憂うつ
-
人と会うのがおっくうに感じる
-
夜なかなか眠れない、あるいは寝すぎてしまう
こうした状態が続くと、自分に対して「ダメだな」と責めたくなってしまうかもしれません。
でも、それはあなたが弱いからではありません。むしろ、それだけがんばってきた証かもしれません。
五月病は「適応の途中で一時的に心が疲れているサイン」とも言えます。
だからこそ、大事なのは「自分に何が起きているのか」を知り、ちょっと立ち止まってみること。
3. なぜ五月病が起きるのか?
「何があったわけでもないのに、心がしんどい」――そんなふうに感じるとき、私たちはつい「気の持ちよう」と思ってしまいがちです。
でも、五月病にはちゃんと理由があります。
ここでは、いくつかの代表的な要因をご紹介します。
1. 環境の変化によるストレス
4月は、進学・就職・異動・引っ越しなど、大きな変化が一気に押し寄せる時期です。
新しい人間関係やルールに適応しようとすることは、それだけで大きなエネルギーを使います。
最初は緊張感とやる気で乗り切れるものの、1ヶ月ほど経った5月になると、気がゆるんだときに反動のように心が疲れていることに気づくのです。
たとえるなら、「マラソンの前半、全速力で走ってしまったような状態」です。
2. がんばりすぎた自分の反動
「早く仕事に慣れなきゃ」「失敗できない」と、自分にプレッシャーをかけ続けると、無意識のうちに心がすり減っていきます。
真面目でがんばり屋さんほど、気づいたときにはエネルギー切れになっていることが多いのです。
特に、周りに合わせようと無理をしていた人は、自分らしさを見失ってしまうこともあります。
「自分って、なんだっけ?」という感覚が出てくるのも、五月病のひとつの特徴です。
3. 自律神経の乱れと生活リズムの崩れ
新生活では、睡眠時間や食事のタイミングが不規則になりがちです。
それによって自律神経のバランスが乱れ、疲れやすさや不安感につながることがあります。
また、休日の過ごし方や、スマホやパソコンの使い方によっても、体内時計がずれてしまい、「寝ても疲れがとれない」と感じる人が増えてきます。
4. 季節の影響も関係しています
春から初夏にかけては、気温や湿度、日照時間などが急激に変化します。
こうした外的な要因も、実は私たちの心や体に少なからず影響を与えています。
とくに日照時間がまだ短めな地域では、気分が落ち込みやすくなることも知られています。
こうした自然のリズムも、心の不調と無関係ではありません。
4. 自分でできるセルフチェック
なんとなく気分が重い日が続いたり、やる気が出ないとき。
「これは疲れてるだけ?それとも、ちょっと注意が必要?」と感じることはありませんか?
そんなときこそ、自分の心と身体の声に耳を傾けてみることが大切です。
ここでは、簡単にできるセルフチェックの方法をご紹介します。答えに正解や不正解はありません。
大切なのは、「今の自分がどんな状態か」に気づくことです。
□ 気づきのためのセルフチェック(10の質問)
以下の項目を読みながら、「あ、ちょっと当てはまるかも」と思うものにチェックを入れてみてください。
-
朝、起きるのがつらく感じる日が増えてきた
-
以前楽しめていたことが、あまり楽しく感じられない
-
頭がぼんやりして、集中できないことがある
-
食欲が落ちたり、逆に食べすぎてしまう日がある
-
人と会ったり話したりするのがおっくうに感じる
-
寝ても疲れがとれない、または眠れない夜がある
-
仕事や勉強に対して、やる気がわかない
-
「なんとなく不安」「気分が晴れない」状態が続いている
-
体が重く感じる、だるさが取れない
-
自分を責めるような気持ちになることがある
□ チェック結果の目安
-
0~2個:今のところ大きな問題はなさそうです。リズムを崩さないように、引き続き自分を大切にしましょう。
-
3~5個:少しお疲れモードかもしれません。ゆっくり休んだり、リフレッシュの時間を意識してとってみてください。
-
6個以上:心が「助けて」と言っているサインかもしれません。無理をせず、信頼できる人や専門家に相談してみることをおすすめします。
□ 気づくことは「やさしさ」の第一歩
チェックの数が多くても、落ち込む必要はありません。
気づけたということは、それだけ自分に目を向けている証拠です。
「自分は今ちょっと疲れてるんだな」と、静かに認めることができれば、それだけでも心は少し軽くなります。
次の章では、そんなときにできるセルフケアの方法をご紹介します。
がんばることより、「ちゃんと休むこと」を大事にしてみませんか?
5. 五月病のセルフケア方法
「最近ちょっとしんどいな」と感じたとき、すぐにできることがあります。
それは、「がんばる」のではなく、「自分をいたわること」。
ここでは、五月病の時期におすすめしたい、やさしいセルフケアの方法をいくつかご紹介します。
1. まずはしっかり眠ること
睡眠は、心と身体を回復させるいちばんの薬です。
寝つきが悪い日が続いていたら、まずは以下のようなことを試してみましょう:
-
夜はスマホやパソコンの画面を早めにオフにする
-
温かいお風呂にゆっくり入る
-
寝る前に部屋を暗くして、静かな音楽やアロマでリラックスする
-
決まった時間に寝て、決まった時間に起きるリズムを意識する
「眠れないときは横になるだけでもOK」と、自分に優しくしてあげてくださいね。
2. 無理なく体を動かす
心が疲れているときこそ、身体を少し動かすことが効果的です。
といっても、無理な運動をする必要はありません。
-
天気のいい日に、近所をゆっくりお散歩する
-
軽いストレッチやヨガをして、深く呼吸する
-
草木や風の匂いを感じながら歩いてみる
自然の中で過ごす時間は、思っている以上に心に効きます。
「5分だけ外に出てみよう」でも、十分な一歩です。
3. 「〜しなければ」を手放してみる
真面目で責任感の強い人ほど、「こうしなければ」「ちゃんとやらなきゃ」と思いがちです。
でも、心が疲れているときは、その「〜ねば」がさらに負担になります。
そんなときは、こう言い換えてみてください:
-
「ちゃんとしなくてもいい。今は休む時期」
-
「できない日があっても大丈夫」
-
「私だけじゃない、誰にでもあること」
完璧じゃなくていい、がんばらなくていい。
自分にそう声をかけるだけでも、少し呼吸がしやすくなります。
4. 心の中を「書いて」整理する
モヤモヤがたまってきたら、ノートやスマホのメモに気持ちを書き出してみるのもおすすめです。
-
「今感じていること」
-
「不安やイライラの理由」
-
「今日うれしかったことや、少しホッとした瞬間」
言葉にすることで、心の中が少し整理されます。誰かに話すのが難しいときでも、自分との対話から癒しが始まることがあります。
5. 小さな「自分らしさ」を取り戻す
毎日の中で、「自分らしい時間」を少しでも取り入れてみましょう。
-
好きな音楽を流す
-
好きな香りのハンドクリームを使う
-
行きたかったカフェに立ち寄る
-
子どもの頃に好きだったことを思い出してやってみる
たとえ10分でも、「自分のための時間」は心の栄養になります。
最後に:がんばらない勇気を
心がつかれているときは、「何もしない」ことも、立派なセルフケアです。
私たちはつい、がんばることが正しいと信じがちですが、
本当に必要なのは「がんばらないことを自分に許す」勇気かもしれません。
「ちょっと疲れたな」と感じたら、立ち止まって、自分を休ませてあげてください。
あなたのペースで大丈夫です。焦らなくても、少しずつ心は回復していきます。
6. 周囲の人との関わり方
― 気持ちを分かち合うことは、心のケアになる ―
心が疲れているとき、「こんなことで悩んでるのは自分だけかも」「人に話すのは迷惑かもしれない」と感じて、つい誰にも言えずに抱え込んでしまうことがあります。けれど、本当はそんなときこそ、人とのつながりが支えになってくれることがあります。
ここでは、心が疲れたときに周囲の人とどう関わっていけばよいか、そのヒントをお伝えします。
1. 「話すこと」そのものが心の栄養になる
気持ちを言葉にすることは、それだけで心の中の重さを少し軽くしてくれます。
特別なアドバイスを求める必要はありません。ただ、「聞いてもらう」だけでいいのです。
-
家族や友人に「ちょっと話を聞いてくれる?」と声をかけてみる
-
内容がまとまっていなくても、「なんとなくしんどくて」と素直に話してみる
-
メッセージやLINEで気軽に近況を送るだけでもつながりは感じられます
相手に気を使ってしまう方も多いかもしれませんが、「話すことを許されている」という体験は、安心感につながります。
2. 助けを求めることは、弱さではなく「知恵」
私たちは「人に頼るのはよくないこと」と思いがちです。でも、本当に心がつらいときに助けを求めることは、むしろ自分を守るための大切な力です。
-
「つらいときは誰かに頼ってもいい」
-
「助けを求めるのは恥ずかしいことではない」
-
「自分ひとりで抱え込まないことが回復への近道」
そう自分に言い聞かせてあげてください。人と人とは、支え合うことで強くなれる存在です。
3. もし周囲の誰かが五月病かもしれないと感じたら
あなた自身だけでなく、家族や友人、同僚が元気をなくしているように感じることもあるかもしれません。そんなときは、無理に励ましたり、解決しようとしたりするよりも、「そばにいるよ」という姿勢が大きな支えになります。
-
「最近、元気ないみたいだけど大丈夫?」とさりげなく声をかける
-
話を聴くときは、アドバイスよりも「うん、そうなんだね」と受け止める
-
無理に元気づけようとせず、ただ一緒にいる時間を大切にする
人は、自分の存在を認めてもらえるだけで心が落ち着いていくものです。
4. 相談できる場所を知っておこう
もし「身近に話せる人がいない」「誰にも打ち明けられない」と感じる場合は、専門的な相談先を頼ってみることも大切です。
-
学校や職場のカウンセラー
-
地域の保健センター
-
メンタルヘルスの電話相談窓口やチャットサービス
-
精神科・心療内科などの医療機関
話を聴いてくれる場所は、思っているよりもたくさんあります。誰かとつながることが、「安心して深呼吸できる場所」になることもあります。
ひとりじゃない。誰かとつながるだけで、心は少し楽になります
心が疲れたとき、「人と関わることすら面倒」と感じるのは自然なことです。
でも、誰かと気持ちを分かち合えたとき、「ああ、私だけじゃなかった」と思える瞬間が必ずあります。
あなたが大切に思う人の言葉やぬくもりが、きっと心にそっと灯をともしてくれるはずです。
7. こんなときは専門家に相談を
― 一人でがんばらなくていい ―
どんなにセルフケアをしていても、つらさがなかなか取れないときがあります。
そんなとき、「自分の努力が足りないのかな」「もっと強くならなきゃ」と、自分を責めてしまう方もいるかもしれません。
でも、それはちがいます。
心の不調は、風邪のように誰にでも起こりうるもの。
そして、専門家の力を借りることは、回復への大切な一歩です。
□ 相談を考えてみてほしいサイン
以下のような状態が続く場合は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
-
2週間以上、気分の落ち込みや無気力が続いている
-
朝起きるのが極端につらく、仕事や学校に行けない日が増えてきた
-
眠れない・食欲がない・体がだるいといった身体症状が強い
-
自分を責める気持ちが強く、「消えてしまいたい」と感じることがある
-
日常生活や人間関係に支障が出てきている
-
誰にも相談できず、孤独感や不安が深まっている
これらのサインは、心が「もう一人で抱えきれない」とSOSを出している証です。
その声に気づいてあげることは、弱さではなく、あなたの「強さ」でもあります。
□ 専門家に相談するって、どんな感じ?
「精神科」や「カウンセリング」という言葉に、少しハードルの高さを感じる方も多いかもしれません。
でも実際には、話を聴いてもらい、今の状況を整理したり、必要に応じて治療や支援を受けられる、安心できる場所です。
相談の場には、次のような選択肢があります:
-
精神科・心療内科:診断や薬の処方を含む医療的なサポート
-
臨床心理士・公認心理師によるカウンセリング:気持ちを整理し、対処方法を一緒に考える時間
-
学校や職場の相談室:比較的身近に利用できる心の相談窓口
-
電話・オンライン相談:家から出られないときにも利用できる手段(地域や団体によって無料のサービスもあり)
初めての相談で不安がある場合は、「最近気分が落ち込むことが多くて」「疲れが抜けなくて」など、話しやすいところからで大丈夫です。
□ 相談することは、「自分を大事にすること」
誰かに頼ることは、自分を甘やかすことでも、逃げることでもありません。
それはむしろ、「自分をきちんと守ろうとする」行動です。
不安やつらさを抱えたまま日々を過ごすのではなく、少し勇気を出して一歩を踏み出すことで、回復の道は開けていきます。
専門家は、あなたのこころの荷物を一緒に持ってくれる存在です。
「ちゃんと話を聞いてもらえる」安心感が、きっと心を少しずつ軽くしてくれるはずです。
8. おわりに
春から初夏へと季節が移り変わるこの時期、気がつかないうちに心や身体が疲れてしまうことがあります。
それは決して、あなたが弱いからでも、努力が足りないからでもありません。
むしろ、「ちゃんとがんばってきた証」かもしれません。
新しい環境に順応しようと、まわりに気を配りながら前に進んできた。
だからこそ、今、少し立ち止まって深呼吸をする時間が必要なのです。
五月病は、一時的な心の疲れが表に出てくる自然な反応です。
そんなときは、「がんばる」ことよりも、「自分をいたわる」ことを大切にしてみてください。
眠ること。
何もしない時間を持つこと。
好きなことに少しだけ触れてみること。
そして、誰かにそっと気持ちを打ち明けること。
どれも小さなことのようでいて、確実に心に効いてくる、大切なセルフケアです。
もし今、ちょっとつらいなと感じている方がいたら――
どうか、自分のペースでゆっくりと。
無理をせず、心の声に耳を傾けてください。
あなたはひとりではありません。
少しずつでも、きっと心は回復していきます。
この記事が、そんな回復のきっかけになれたなら、とても嬉しく思います。
今日という日が、あなたにとって少しでも穏やかな一日になりますように。
■オンライン診療メンタルヘルス院について■
休職相談を扱う"オンライン診療専門"の
「オンライン診療メンタルヘルス院」もあります。
休職について悩まれている方は、お気軽にご相談ください。