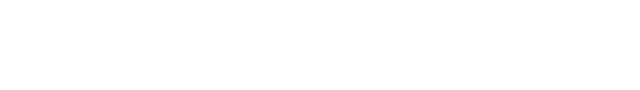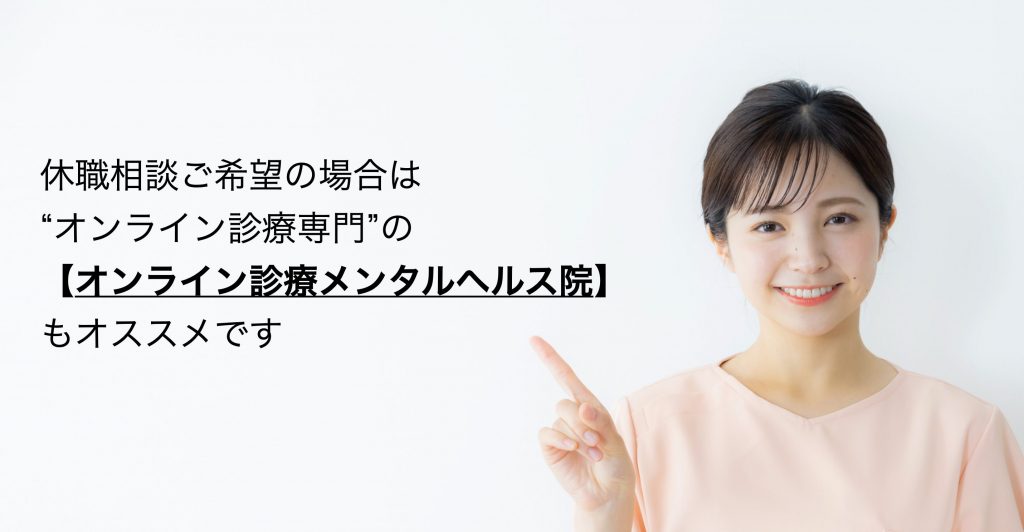ストックホルム症候群とは??
ストックホルム症候群とは?
ストックホルム症候群(Stockholm Syndrome)は、犯罪や虐待の被害者が加害者に対して強い共感、親近感、さらには依存心を抱くようになる心理的現象です。
この症状は誘拐、監禁、虐待、ドメスティックバイオレンス(DV)などの極限状況で発生することが多いとされています。
被害者が加害者を擁護するような行動を取る場合もあり、客観的には矛盾した行動に見えるため、理解が難しい心理現象として注目されています。
ストックホルム症候群の起源
この名称の由来は、1973年にスウェーデンの首都ストックホルムで起きた銀行強盗事件です。この事件では、銀行強盗が人質を取り、6日間にわたり銀行内に立てこもりました。人質たちは加害者と長時間を過ごす中で次第に彼らに親近感を抱くようになり、事件解決後も加害者を擁護する発言をしました。
さらに、人質たちは救出者である警察に対して不信感を抱き、加害者との関係を守ろうとする行動を取ったため、心理学的に大きな注目を集めました。このような特殊な被害者心理が「ストックホルム症候群」として命名され、以後、犯罪心理学やトラウマ研究の分野で頻繁に議論されるようになりました。
ストックホルム症候群の心理的メカニズム
ストックホルム症候群が発生する背景には、さまざまな心理的な要因が絡み合っています。以下にその主要なメカニズムを解説します。
1. 生存本能と適応行動
被害者が極限的な状況に置かれると、最優先となるのは生存です。そのため、加害者の要求に従い、敵対的な行動を避けることで命の危険を減らそうとする心理が働きます。加害者の機嫌を取ったり、協力的な態度を示したりするうちに、加害者に対する恐怖が徐々に薄れ、親近感へと変わる場合があります。
2. 依存関係の形成
加害者が支配者として振る舞う中で、被害者は完全に加害者に依存する状況に陥ります。このような状況下では、加害者が示す小さな親切や優しさが非常に大きな意味を持つように感じられます。その結果、被害者は加害者を信頼し、心理的に頼るようになります。
3. 感情の合理化と自己防衛
被害者は極度のストレスや恐怖を感じながらも、それに対処するために状況を肯定的に捉えようとします。加害者を好意的に見ることで、心理的な負担を軽減しようとするのです。これが感情の合理化という現象です。
4. 孤立感と連帯感
被害者が外部の支援から切り離され、加害者と長時間を過ごす場合、孤立感が強まります。この状況で、加害者との間に共通の「敵」――たとえば警察や社会――がいると感じると、被害者は加害者に対する連帯感を抱くことがあります。
主な特徴と症状
ストックホルム症候群に見られる典型的な特徴や症状を以下に挙げます。
-
加害者への同情や擁護
-
被害者が加害者の行動を正当化し、擁護する。
-
加害者に対する刑罰を望まない、または減刑を訴える。
-
-
依存と信頼の形成
-
被害者が加害者を信頼し、心理的に頼る。
-
加害者を安全な存在と感じる。
-
-
救助者や第三者への不信感
-
被害者が警察や救助隊、家族などの支援者に対して敵意を抱く。
-
自分を助けようとする人々よりも加害者を信用する。
-
-
現実認識の歪み
-
被害者が状況を客観的に判断できなくなり、加害者との関係を肯定的に捉える。
-
自分の置かれている危険な状況に気づかない、または意識しない。
-
発生しやすい状況
ストックホルム症候群が発生するのは、特定の条件が整った場合です。以下に、その典型的な状況を示します。
誘拐や監禁事件
人質が長時間にわたり加害者と接触し、命の危険にさらされる状況。
ドメスティックバイオレンス(DV)
配偶者やパートナーからの暴力を受けている被害者が、加害者に依存する心理状態。
カルト宗教や洗脳
閉ざされたコミュニティ内で、指導者や支配者に強い忠誠心を抱くケース。
性的搾取や人身売買
被害者が加害者に依存せざるを得ない環境に置かれることで、ストックホルム症候群が発生することがあります。
治療と回復
ストックホルム症候群からの回復には、時間と適切なサポートが必要です。以下は主な治療と回復の方法です。
1. 心理療法
心理カウンセリングや認知行動療法(CBT)を通じて、被害者の感情や認知を整理し、正常な視点を取り戻す手助けをします。
2. 安全な環境の提供
被害者が安心して暮らせる環境を提供することが重要です。加害者から物理的に距離を置くことで、心理的依存関係を断ち切ることが可能になります。
3. トラウマ治療
多くの被害者はPTSD(心的外傷後ストレス障害)を経験します。これには、EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)や他のトラウマ治療技法が有効です。
4. 社会的サポートの活用
被害者が孤立しないよう、家族や友人、専門家による支援が必要です。また、被害者支援団体やカウンセリングサービスを利用することも推奨されます。
社会的意義
ストックホルム症候群の理解は、犯罪被害者への偏見や誤解を減らすために重要です。この症候群を正しく理解することで、被害者の行動を非難するのではなく、共感し、適切な支援を提供することが可能になります。また、犯罪心理学やトラウマ研究の分野においても、この現象を研究することで、被害者の支援体制の改善や犯罪防止策の強化につながるとされています。
被害者心理に関心がある方や支援を考えている方にとって、ストックホルム症候群についての深い理解は非常に有益です。
■オンライン診療メンタルヘルス院について■
休職相談を扱う"オンライン診療専門"の
「オンライン診療メンタルヘルス院」もあります。
休職について悩まれている方は、お気軽にご相談ください。