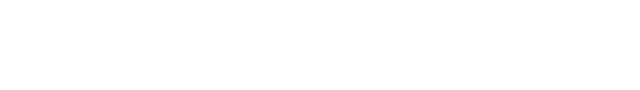新型コロナウイルス感染症の後遺症(メンタル面)
[2023.12.12]
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の後遺症において、メンタルヘルスへの影響は多岐にわたり、深刻な問題となっています。
以下に、その具体的な側面をさらに詳しく説明します。
-
不安とストレス:
- 感染経験者は、健康への懸念や再感染の不安により、高いストレスを感じることがあります。
- 経済的な不安、仕事の喪失、社会的関係の変化など、パンデミックによる広範囲な影響も、ストレスの原因となり得ます。
- 長期間にわたる症状(長引く咳、疲労感など)は、日常生活への不安を増幅させる可能性があります。
-
うつ症状:
- COVID-19による隔離や社会的距離の確保は、孤立感や孤独感を引き起こし、うつ症状を悪化させることがあります。
- 長期間続く身体的な苦痛や活動制限も、うつのリスクを高める要因です。
- 回復後も続く身体的な制限や活動の変化は、自己価値感の低下を招き、うつ症状を引き起こすことがあります。
-
睡眠障害:
- 睡眠の質の低下や不眠症は、COVID-19の回復者によく見られる症状です。
- ストレス、不安、うつ症状が睡眠パターンに悪影響を及ぼすことがあります。
- 睡眠障害は、日中の機能や気分に影響を与え、回復過程を遅らせる可能性があります。
-
認知機能の問題:
- 集中力の欠如、記憶障害、判断力の低下など、認知機能に関する問題が発生することが報告されています。
- これらの問題は、「COVID-19の脳霧」とも呼ばれ、日常生活や職業生活に支障をきたすことがあります。
-
PTSD(心的外傷後ストレス障害):
- 重症のCOVID-19を経験した人々、特に集中治療室(ICU)での治療を受けた人々は、PTSDの症状を示すリスクが高いです。
- これには、悪夢、フラッシュバック、過度の警戒心などが含まれます。
- COVID-19に関連する死亡や重篤な病気の経験も、PTSDのリスクを高める可能性があります。
これらの心理的影響は、感染後数週間から数ヶ月にわたって続くことがあり、回復の過程は個人差が大きいです。
一部の人々には長期間にわたるサポートや治療が必要です。
これらの症状に対処するためには、適切な休息、ストレス管理、社会的サポート、専門家によるカウンセリングや治療が重要です。